Ⅴ-4.下鼻甲介手術の限界
下鼻甲介粘膜凝固術も下鼻甲介切除術も、開始されて以来1世紀以上が経過しています。しかしながら現在においてもなお、用いられている術式はまちまちで、治療効果の確かなスタンダードとなる手術法は確立していません。この事実は、下鼻甲介を対象とした手術治療には一定の限界があることを示しているものと思われます。
では、この限界とはいったい何なのでしょうか?
第一に、前述したように慢性鼻炎に起因する「鼻づまり」は、鼻腔の広い範囲の粘膜が腫れることによっておこる症状です。これに対して、下鼻甲介手術はその周囲の間隙だけを作り出す手術であり、例え下鼻甲介のすべてを切除したとしても、容積的には、本来の鼻腔の2分の1程度の間隙しか確保できません。さらに、吸い込まれた空気は、下鼻甲介周囲ではなく、主に中鼻甲介周囲に流れ込むとされています[文献10]。したがって、中鼻甲介の周囲の間隙を再形成しない限り、十分な通気性を取り戻すことはできません[図Ⅴ-4-1]。
図Ⅴ-4-1
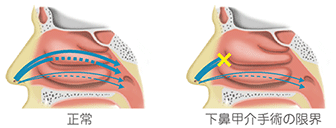
第二は、慢性鼻炎の粘膜病変は治りにくく、粘膜を凝固あるいは切除しても、再びもとの状態に戻ることが少なくないことです。そして第三は、―小児にとってはこれが最も重要な点ですが―、下鼻甲介は、その形態も、また下鼻甲介を覆う粘膜も、鼻の機能にとって重要な役割を果たしていることです。それは、吸い込まれた空気の流れる方向性を決める舵のような働きであり、これが広い範囲の粘膜と空気との接触を促し、温度や湿度を粘膜から効率的に受け取り、空気中の有害物質を除去し、また、嗅覚神経が分布している鼻腔の天井部にある狭い隙間(嗅裂)へと空気が入り込むのを可能にします(⇒「呼吸器としての鼻」、「鼻づまりの弊害-嗅覚障害」の項を参照)。下鼻甲介に何らかのダメージを与えることは、このような機能を損ねることにほかなりません。
下鼻甲介手術は、下鼻甲介の容積を減少させることを目的とした手術であり、粘膜を切除する方法にしろ、あるいは骨組織を切除する方法にしろ、程度の差こそあれ粘膜あるいは形態の破壊を避けることはできません。要するに、下鼻甲介手術は、 "機能の保存" と "効果の獲得" のバランスの上に成立している手術であり、両者を両立できない以上、その効果にはおのずと限界があるわけです。
上記したように、粘膜凝固術あるいは切除術の治療効果についての報告は(ほとんどが1年以内の短期治療効果についてであるものの)、いずれも80%以上の有効率を示しています。しかしこの数値が、80%の「鼻づまり」が治ることを示しているわけではありません。これを裏付けるように、イスラエルのテル・アヴィヴゥ大学から、3~10歳の小児を対象とした下鼻甲介全切除術(下鼻甲介のすべてを切除する手術)を行った治療成績と、その有用性を強調した報告が2003年に出されています[文献37]。この手術は、鼻腔の下半分がからっぽになることからempty nose syndromeと呼ばれる後遺症―ひどい「鼻づまり感」や乾燥感―をきたす危険性があり[図Ⅴ-4-2]、通常は用いられない手術です。このような手術が小児に対しても用いられている事実は、下鼻甲介手術のもつ効果の限界を示しているといえます。
図Ⅴ-4-2

10) Van Cauwenberge P, Sys L, De Belder T, et al. Anatomy and physiology of the nose and the paranasal sinuses. Immunol Allergy Clin North Am 24(1):1-17,2004.
37) Segal S, Eviatar E, Berenholz L, et al. Inferior turbinectomy in children. Am J Rhinol 17:69-73, 2003.
